【実例公開】売り上げを伸ばしている飲食店の成功戦略とは?コロナ禍でも50%増の店舗が実践する具体的手法

はじめに
コロナ禍という未曽有の困難を経験した飲食業界において、多くの店舗が苦戦を強いられる中、逆に売上を大幅に伸ばした飲食店も数多く存在しています。これらの成功店舗は、変化する消費者のニーズを的確に捉え、柔軟な対応力と創意工夫により新たな価値を創造してきました。
売上アップを実現した飲食店の成功事例を分析すると、デリバリーサービスの拡充、メニューの見直し、デジタル技術の活用など、時代に即した戦略的な取り組みが共通しています。本記事では、これらの成功店舗が実践した具体的な手法と戦略について詳しく解説し、飲食店経営者の皆様にとって実践的な指針となる情報をお届けします。
売上アップの基本構造
飲食店の売上は「客数×客単価」という基本的な公式で算出されます。この公式を理解することは、売上アップのための戦略を立てる上で最も重要な出発点となります。成功している飲食店は、この基本構造を深く理解し、どちらか一方だけでなく、両方の要素を同時に改善する取り組みを行っています。
例えば、月商57万円の大ヒットを記録した「蕎麦前酒場 はんさむ渋谷」では、女性客向けのレディースメニューを開発することで新たな客層を獲得し、客数の増加を実現しました。同時に、自慢の食材の紹介や提供時の演出にこだわることで、顧客満足度を高め、客単価の向上にも成功しています。このように、客数と客単価の両方にアプローチすることで、相乗効果を生み出すことができるのです。
データ分析の重要性
売上を継続的に伸ばしている飲食店の共通点として、データに基づいた経営判断を行っていることが挙げられます。坪単価の把握、毎月の売上予測の立案、実績との比較分析など、数値を活用した科学的なアプローチが成功の鍵となっています。これにより、どこを改善すべきかが明確になり、効果的な施策を打つことができます。
また、来店動機の分析も重要な要素です。顧客がなぜその店を選んだのか、何を求めて来店したのかを深く理解することで、より効果的なメニュー開発やサービス改善につなげることができます。データ分析を通じて、感覚的な経営から脱却し、確実性の高い戦略的経営へと転換することが、売上アップの基盤となるのです。
時代変化への対応力
コロナ禍を経験した飲食業界では、従来の営業スタイルに固執せず、時代の変化に柔軟に対応できる店舗が生き残り、さらに成長を遂げています。約6割の成功店舗で10%~50%の売上増加が見られ、3割近くの店舗では50%以上の大幅な売上増加を達成しているというデータは、適応力の重要性を物語っています。
これらの成功店舗は、巣ごもり消費の増加、非接触サービスへのニーズ、健康志向の高まりなど、社会情勢の変化を機会として捉え、新たなビジネスモデルを構築しました。変化を恐れず、むしろチャンスとして活用する姿勢が、売上アップを実現する原動力となっているのです。
コロナ禍で成功した戦略的アプローチ

コロナ禍という未曽有の危機は、飲食業界に大きな変革をもたらしました。しかし、この困難な状況下でも売上を伸ばした飲食店は、危機を機会に変える戦略的思考と迅速な行動力を発揮しました。これらの成功店舗が実践した戦略的アプローチを分析することで、今後の飲食店経営における重要な指針を見出すことができます。
デリバリーサービスの戦略的拡充
コロナ禍で最も注目された取り組みの一つが、デリバリーサービスの拡充です。成功した飲食店は、単純にデリバリーを始めるだけでなく、デリバリー専用メニューの開発、包装方法の工夫、配達時間の短縮など、総合的なサービス向上に取り組みました。全メニューでテイクアウトが可能になるよう調理法を見直したり、持ち帰り時の品質保持にこだわったりすることで、店内飲食と変わらない満足度を提供することに成功しています。
また、デリバリーサービスの成功には、注文プロセスの簡素化も重要な要素となりました。オンライン注文システムの導入、電話注文の効率化、事前注文システムの活用など、顧客が簡単に注文できる環境を整備することで、新たな客層の獲得と既存客の利用頻度向上を同時に実現しています。これらの取り組みにより、店舗の売上チャネルを多様化し、安定した収益基盤を構築することができました。
メニュー戦略の抜本的見直し
コロナ禍での成功店舗は、従来のメニューに固執することなく、新しい生活様式に適応したメニュー開発を積極的に行いました。提供時間の短いメニューの増加、個包装に適した料理の開発、家族向けの大容量メニューの追加など、変化する消費者ニーズに対応した商品ラインナップを早期に整備しています。これにより、巣ごもり消費の需要を的確に捉え、売上の維持・向上を実現しました。
特に注目すべきは、期間限定メニューや裏メニューなど、話題性の高い商品開発に力を入れた点です。「限定」という言葉に対する消費者心理を巧みに活用し、SNSでの拡散効果も狙った戦略的なメニュー開発が、新規客の獲得と既存客のリピート率向上に大きく貢献しています。このような創造的なアプローチにより、コロナ禍という制約の中でも、顧客の興味と関心を引き続けることができたのです。
デジタルテクノロジーの積極活用
成功した飲食店のもう一つの共通点は、デジタルテクノロジーを積極的に活用している点です。POSレジシステムの導入、セルフオーダーシステムの活用、予約顧客管理システムの導入など、業務効率化と顧客サービス向上の両方を実現するツールを効果的に活用しています。これにより、限られた人員でも質の高いサービスを提供し続けることが可能になりました。
また、オンラインシステムの活用は、顧客データの収集と分析にも大きなメリットをもたらしています。顧客の注文履歴、来店頻度、好みの傾向などを詳細に把握することで、個々の顧客に最適化されたサービスを提供できるようになりました。この「おもてなしの向上」が顧客満足度の向上につながり、結果として売上増加に大きく寄与しているのです。
客数増加のための実践的手法

飲食店の売上向上において、客数の増加は最も直接的で効果的なアプローチの一つです。しかし、単純に広告を増やすだけでは持続的な客数増加は望めません。成功している飲食店は、戦略的かつ体系的なアプローチにより、新規客の獲得とリピーター化を同時に実現しています。ここでは、実際に成果を上げている具体的な手法について詳しく解説します。
店舗コンセプトの明確化と差別化
客数増加の基盤となるのは、明確で魅力的な店舗コンセプトの構築です。成功店舗の多くは、ターゲット客層を明確に定義し、その客層のニーズに特化したコンセプトを打ち出しています。例えば、これまで営業していなかった時間帯の営業開始、特定の客層に向けたメニュー開発、店内の雰囲気作りなど、コンセプトに基づいた一貫性のある取り組みを行っています。
また、他店との差別化を図るために、独自性の高いサービスや商品を開発することも重要です。コラボ企画の実施、オリジナルメニューの開発、特別な演出やサービスの提供など、競合店では体験できない価値を創造することで、顧客の記憶に残りやすい店舗となります。このような差別化戦略により、口コミやSNSでの拡散効果も期待でき、自然な形での集客力向上を実現できるのです。
効果的な情報発信とマーケティング
現代の飲食店経営において、SNSやWebサイトを活用した情報発信は不可欠な要素となっています。成功している店舗は、単に料理の写真を投稿するだけでなく、店舗の世界観や雰囲気を伝える戦略的なコンテンツ制作を行っています。バーチャルツアーの活用、スタッフの人柄が伝わる投稿、調理過程の紹介など、多角的なアプローチにより顧客との関係性を深めています。
また、季節に合わせたキャンペーンやイベントの企画も効果的な集客手法です。「いい肉の日」セールのような話題性の高いイベント、誕生日限定クーポンの配布、季節限定メニューの提供など、顧客が来店する理由を定期的に創出することで、継続的な集客効果を実現しています。これらの取り組みを通じて、顧客との接点を増やし、長期的な関係構築につなげることができます。
地域密着型マーケティングの実践
客数増加のためには、地域コミュニティとの深いつながりを築くことも重要な戦略です。出前や出張サービスの提供により、店舗の存在を地域に広くアピールし、新たな顧客層にリーチすることができます。また、地域のイベントへの参加、近隣企業との連携、地元食材の積極的な活用など、地域密着型の取り組みを通じて、コミュニティ内での認知度と信頼度を高めています。
さらに、メディア露出の機会を積極的に求めることも効果的です。地域のテレビ番組、雑誌、新聞などに取り上げてもらうための工夫や、話題性の高い取り組みの実施により、広範囲にわたる認知度向上を図ることができます。このような地域密着型のマーケティングは、コストパフォーマンスが高く、持続的な効果が期待できる手法として、多くの成功店舗で実践されています。
客単価向上の戦略的取り組み

客単価の向上は、売上アップを実現するもう一つの重要な柱です。新規客を獲得するよりも既存客の客単価を上げる方が効率的であることが多く、持続的な収益性向上に直結します。成功している飲食店は、顧客満足度を損なうことなく、自然な形で客単価を向上させる巧妙な戦略を展開しています。
メニュー構成の戦略的設計
客単価向上の基盤となるのは、戦略的に設計されたメニュー構成です。セット商品の充実、コース料金の適正化、サブメニューの拡充など、顧客が追加注文しやすい環境を整備することが重要です。特に、メイン料理に加えてサイドメニューやドリンクを組み合わせたセットメニューは、単品注文よりも高い客単価を実現しながら、顧客にとってもお得感のある価格設定が可能になります。
また、料理のランクアップやオプション機能の充実も効果的な手法です。通常メニューに加えて、より高品質な食材を使用したプレミアムバージョンを用意したり、トッピングやサイズアップなどのオプションを豊富に取り揃えることで、顧客の多様なニーズに対応しながら客単価の向上を図ることができます。これにより、同じ料理でも幅広い価格帯での提供が可能になり、様々な顧客層に対応できるようになります。
サービス品質と演出力の向上
客単価向上には、料理の品質だけでなく、サービス全体の価値向上が重要な役割を果たします。スタッフのおすすめスキルの向上、料理の提供時における演出、自慢の食材や調理法の紹介など、顧客が「特別な体験」を感じられるようなサービス提供が求められます。これにより、同じ料理でもより高い価値を感じてもらい、自然な形でのアップセルが可能になります。
特に、接客時の声掛けは客単価向上に大きな影響を与えます。メニューのランキング化、季節のおすすめ料理の紹介、ペアリングの提案など、顧客が追加注文したくなるような適切なタイミングでの提案が重要です。ただし、押し売り的なアプローチではなく、顧客の満足度向上を第一に考えた自然なコミュニケーションが成功の鍵となります。
顧客体験の総合的な向上
客単価の持続的な向上には、顧客体験全体の質を高めることが不可欠です。店頭ディスプレイの工夫、店内告知や差し込みメニューの効果的な活用、注文しやすい環境づくりなど、顧客が快適に過ごし、自然に追加注文したくなるような環境整備が重要です。これらの取り組みにより、顧客満足度を高めながら売上向上を実現できます。
また、ミニイベントの実施や特別な演出により、通常の食事体験を超えた価値を提供することも効果的です。記念日向けの特別サービス、シェフとの交流機会、限定メニューの試食会など、特別感のある体験を提供することで、顧客はより高い金額を支払うことに納得感を持てるようになります。このような総合的なアプローチにより、一時的ではない持続的な客単価向上を実現できるのです。
業務効率化とサービス改善の両立

売上向上を実現するためには、業務効率化とサービス品質の向上を同時に実現することが重要です。限られた人員とコストの中で最大限の成果を出すためには、テクノロジーの活用と人的サービスの最適な組み合わせが求められます。成功している飲食店は、この両立を巧みに実現し、持続可能な成長を遂げています。
テクノロジー導入による業務改革
現代の飲食店経営において、テクノロジーの活用は業務効率化の中核となっています。セルフオーダーシステムの導入により、注文受付にかかる人員を削減しながら、注文ミスの減少と処理速度の向上を実現しています。また、POSレジシステムの活用により、売上データの自動集計、在庫管理の効率化、顧客情報の一元管理が可能になり、経営判断に必要な情報を迅速に取得できるようになりました。
予約顧客管理システムの導入は、特に顧客サービスの向上に大きな効果をもたらしています。顧客の来店履歴、好みの料理、アレルギー情報などを事前に把握することで、個別最適化されたサービスを提供できるようになります。これにより、顧客満足度の向上とリピート率の増加を実現し、結果として売上向上に直結する成果を得ています。
人員配置の最適化と教育体制
業務効率化においては、テクノロジーの導入だけでなく、人員配置の見直しも重要な要素です。店舗の混雑状況や時間帯別の客数データを分析し、最適な人員配置を実現することで、サービス品質を維持しながらコスト削減を図ることができます。また、スタッフの多能工化を進めることで、状況に応じた柔軟な対応が可能になり、効率的な店舗運営を実現しています。
さらに、スタッフの教育体制の充実により、一人一人のスキル向上を図ることも重要です。効率的な動線の習得、適切な声掛けのタイミング、商品知識の向上など、総合的なスキルアップにより、少ない人数でも高品質なサービスを提供できるようになります。これにより、人件費の適正化と顧客満足度の向上を同時に実現することができるのです。
オペレーション改善による生産性向上
業務効率化の実現には、日常的なオペレーションの継続的な改善が不可欠です。事前の仕込み作業の効率化、調理工程の標準化、提供時間の短縮など、細かな改善の積み重ねが大きな効果をもたらします。成功店舗では、定期的に店舗の状況を振り返り、ボトルネックとなっている工程を特定し、具体的な改善策を実施しています。
また、店内が混雑した際の対応手順の明確化、注文機会を逃さないための仕組み作りなど、売上向上に直結するオペレーション改善も重要です。これらの取り組みにより、同じ時間と人員でもより多くの客数を受け入れることができ、結果として売上向上と効率化の両立を実現しています。継続的な改善活動により、競合店との差別化も図ることができるのです。
成功事例に学ぶ実践的ノウハウ

理論だけでなく、実際に成果を上げた具体的な成功事例から学ぶことで、より実践的で効果的な施策を展開することができます。ここでは、売上向上を実現した飲食店の具体的な取り組みと、その背景にある戦略的思考について詳しく解説します。これらの事例は、業態や規模の違いを超えて応用可能な普遍的なノウハウを含んでいます。
大手チェーン店の戦略的アプローチ
飲食業界の売上上位企業であるゼンショーホールディングス、日本マクドナルドホールディングス、すかいらーくホールディングスなどは、それぞれ独自の戦略により持続的な成長を実現しています。ゼンショーホールディングスは独自のビジネスモデルと世界規模の食材調達によるスケールメリットを活かし、売上1兆1,366億円という驚異的な数字を達成しています。このような規模の経済効果は、中小規模の飲食店でも地域レベルでの共同仕入れや業務提携により、一定程度実現可能な手法です。
日本マクドナルドホールディングスの戦略は、単価を下げつつクロスセル商品の販売で利益を確保するという巧妙なアプローチです。メイン商品で顧客を惹きつけ、サイドメニューやドリンクで収益を確保するこの手法は、多くの飲食店で応用可能な戦略です。売上4,054億円を達成した背景には、このような緻密な価格戦略と商品構成の最適化があることを理解し、自店舗でも活用できる要素を見出すことが重要です。
中小規模店舗の創意工夫
「蕎麦前酒場 はんさむ渋谷」の成功事例は、中小規模の飲食店にとって非常に参考になる事例です。月商57万円という大ヒットを記録した同店では、来店動機の詳細な分析に基づき、女性客向けのレディースメニューを開発し、これまでリーチできていなかった客層の獲得に成功しました。この事例が示すのは、既存の枠組みにとらわれることなく、新しい客層のニーズを発掘し、それに応える商品開発の重要性です。
同店のもう一つの特徴は、自慢の食材の紹介や提供時の演出にこだわった点です。料理の単純な提供ではなく、ストーリーを伝える演出により、同じ料理でもより高い価値を感じてもらう工夫を行いました。また、SNSを活用した積極的な情報発信により、店舗の魅力を効果的に伝え、集客力を高めています。これらの取り組みは、大きな投資を必要とせず、創意工夫により実現可能な手法として、多くの店舗で参考になるでしょう。
業態別成功パターンの分析
異なる業態の成功事例を分析することで、自店舗に適用可能な成功パターンを見出すことができます。割烹料理店の阿吽がバーチャルツアーを導入した事例は、高級業態でもデジタル技術の活用が効果的であることを示しています。店の細部や雰囲気を事前に伝えることで、来店への期待値を高め、実際の体験での満足度向上につなげています。
一方、回転寿司チェーンのかっぱ寿司がLINE公式アカウントを活用した事例や、焼肉店の牛角が「いい肉の日」セールを行った事例は、チェーン店でもローカル店でも応用可能な手法を示しています。顧客との継続的なコミュニケーション手段の確保、話題性の高いイベントの企画など、業態を問わず効果的な手法があることがわかります。これらの成功パターンを自店舗の特性に合わせてカスタマイズすることで、効果的な施策を展開することができるのです。
まとめ
飲食店の売上向上を実現するためには、多角的かつ戦略的なアプローチが不可欠であることが明らかになりました。コロナ禍という困難な状況下でも売上を伸ばした飲食店の成功事例を分析すると、共通して「変化への適応力」「顧客ニーズの深い理解」「テクノロジーの効果的活用」「継続的な改善意識」という4つの要素が重要な役割を果たしています。
特に重要なのは、「客数×客単価」という基本構造を理解した上で、両方の要素を同時に改善する取り組みを行うことです。デリバリーサービスの拡充、メニューの戦略的見直し、デジタルテクノロジーの活用、効果的な情報発信など、複数の施策を組み合わせて実践することで、相乗効果を生み出すことができます。また、業務効率化とサービス品質向上の両立により、持続可能な成長基盤を構築することも重要です。
成功事例から学べる最も重要な教訓は、固定観念にとらわれることなく、顧客の変化するニーズに柔軟に対応し続けることの大切さです。大手チェーン店から個人経営の小さな店舗まで、規模や業態を問わず、創意工夫と戦略的思考により売上向上を実現できる可能性があることが示されました。今後の飲食店経営においては、これらの成功要因を自店舗の特性に合わせて適用し、継続的な改善を重ねていくことが、持続的な成長への道筋となるでしょう。
よくある質問
売上を伸ばすために重要なのは何ですか?
売上を伸ばすためには、「客数×客単価」という基本構造を理解し、両方の要素を同時に改善する取り組みが重要です。デリバリーサービスの拡充、メニューの戦略的見直し、デジタルテクノロジーの活用、効果的な情報発信など、複数の施策を組み合わせて実践することで、相乗効果を生み出すことができます。
飲食店の成功事例から何が学べますか?
飲食店の成功事例からは、「変化への適応力」「顧客ニーズの深い理解」「テクノロジーの効果的活用」「継続的な改善意識」という4つの要素が重要であることが学べます。大手チェーン店から個人経営の小さな店舗まで、規模や業態を問わず、創意工夫と戦略的思考により売上向上を実現できる可能性があります。
データ分析の重要性はどのようなことが言えますか?
売上を継続的に伸ばしている飲食店では、数値を活用した科学的なアプローチが成功の鍵となっています。坪単価の把握、売上予測の立案、実績との比較分析など、データに基づいた経営判断を行うことで、効果的な施策を打つことができます。また、来店動機の分析も重要で、顧客の求めているものを深く理解することが、メニュー開発やサービス改善につながります。
業務効率化とサービス向上を両立するには何が重要ですか?
売上向上を実現するためには、業務効率化とサービス品質の向上を同時に実現することが重要です。テクノロジーの活用と人的サービスの最適な組み合わせにより、限られた人員とコストの中で最大限の成果を出すことができます。具体的には、セルフオーダーシステムの導入や人員配置の最適化、スタッフの教育体制の充実などが効果的です。この両立により、持続可能な成長基盤を構築できます。
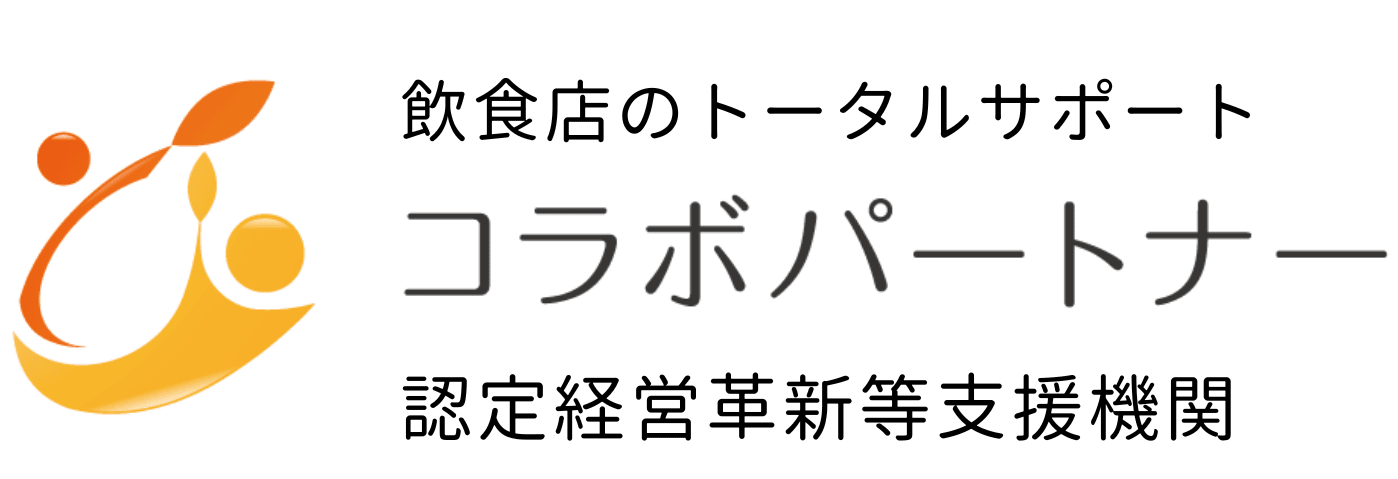
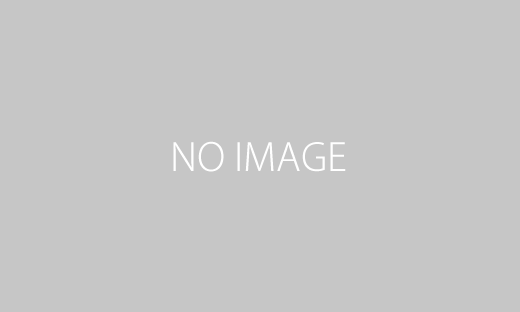

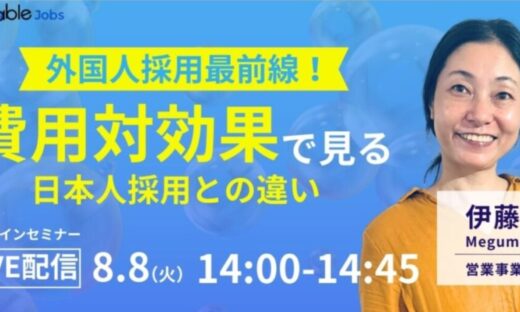






この記事へのコメントはありません。