第5回:メニュー改善と商品管理で利益率アップ

この記事でわかること
- 売上と利益率向上のための「メニュー改善」と「商品管理」の方法
- 特に利益率の高いメニューの選定や、食材管理の最適化について
1.メニュー改善のポイント
メニューの内容や構成を工夫することで、売上と利益の最大化が可能です。
書籍では「顧客満足度を向上させながら、利益率を確保するメニュー設計が重要」と述べています。
(1) 商品管理のABC分析を活用する
ABC分析とは、メニューを 売上構成比・出数・粗利 の3つの観点から評価する手法です。
これにより、売上貢献度が高い商品と低い商品を明確にできます。
ランク特徴具体例
| Aランク商品(主力商品) | 売上・利益ともに高い | 看板メニュー、人気の定番商品 |
| Bランク商品(育成商品) | そこそこの売上・利益だが、伸びしろあり | 季節限定メニュー、新メニュー |
| Cランク商品(低収益商品) | 売上も利益も低く、提供価値が低い | あまり注文されないメニュー |
ABC分析の実践方法
- 1カ月の販売データを集計し、各メニューの販売数・売上・粗利を算出する。
- それぞれの数値をもとに、A・B・Cの3つのランクに分類する。
- Aランク商品をさらに強化し、Cランク商品は改善・削減を検討する。
実践例:
ある店舗では、ABC分析を実施した結果、Cランクに分類された「低利益・低販売数」のメニューを削減。
その分、Aランクの人気メニューのバリエーションを増やしたところ、売上が15%向上した。
(2) 商品ストーリーを明確化し、価値を高める
「なぜこの商品を提供するのか?」を明確に伝えることで、顧客の購入意欲を高められます。
商品ストーリーの要素
- こだわりのポイント:使用する食材や調理方法の工夫を伝える。
- 誕生の背景:メニュー開発の経緯やシェフの想いを伝える。
- 食べるメリット:健康や美容への効果、特別な体験を訴求する。
実践例:
「当店のハンバーグは、国産和牛100%を使用し、赤ワインでじっくり煮込んだ特製ソースで仕上げています。口の中でとろける食感をぜひお楽しみください!」
このようなストーリーをメニュー表やPOPで伝えることで、単価の高いメニューでも納得感を持って注文してもらえます。
2. 商品管理の最適化
1.で行ったメニューの改善に加えて、商品管理を最適化することでコスト削減と利益率向上を図ります。
(1) 食材ロスを削減する
- 需要予測を基に仕入れを調整:過去の販売データを活用し、適正な仕入れ量を設定する。
- 保存管理の徹底:冷蔵・冷凍の管理方法を見直し、廃棄を減らす。
- Cランク商品の活用:低売上のメニューの食材を、他のメニューに転用する。
実践例:
ある店舗では、余剰食材を使った「日替わり小鉢」を提供し、食材ロスを30%削減しながら追加売上を確保した。
(2) 原価率を意識した価格設定
- 利益率の高いメニューを増やす:原価率が低く、付加価値の高いメニューを重点的に販売する。
- セットメニューの導入:原価率の高い単品商品を、利益率の高いドリンクやサイドメニューと組み合わせる。
実践例:
ハンバーガー単品(原価率40%)に、フライドポテトとドリンクをセットにし、セット価格で販売。結果、客単価が15%向上した。
3. 成果を確認するための指標
施策を実施した後には、その効果を測定することが重要です。
以下の指標を定期的にチェックし、改善を繰り返しましょう。
売上と利益率の推移
- ABC分析を定期的に実施し、売上・利益の向上状況を確認する。
- 目標として、利益率5%以上の改善を目指す。
食材ロスの削減率
- 廃棄食材の量を記録し、削減率をチェックする。
- 目標として、廃棄率10%以下を目指す。
メニューごとの販売数
- 期間限定メニューやセットメニューの販売数を計測し、効果を分析する。
4.まとめと全5回の振り返り
メニュー改善と商品管理を最適化することで、利益率を向上させ、安定した売上を確保できます。
特に、ABC分析を活用したメニュー選定や、食材ロス削減の取り組みは、経営の効率化に直結します。
これまでのシリーズでは、飲食店の固定客化と経営改善のために、以下のテーマを解説してきました。
- 第1回:固定客化の重要性
- 第2回:ボトムファネル戦略
- 第3回:QSCAとNPSの活用
- 第4回:スタッフ教育とコンタクトポイントの改善
- 第5回:メニュー改善と商品管理の最適化
これらの施策を組み合わせることで、売上の安定化と経営の効率化を実現できます。
あなたの店舗でも、今日から実践できる施策を取り入れてみてはいかがでしょうか?
今後の成功に向けて、一歩ずつ確実に取り組んでいきましょう!
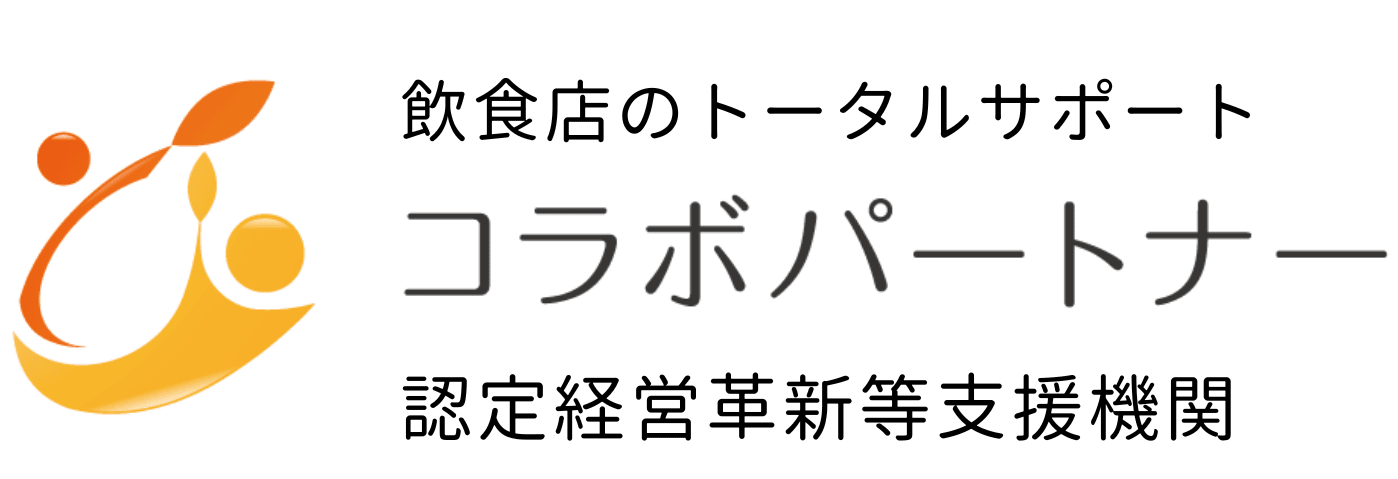


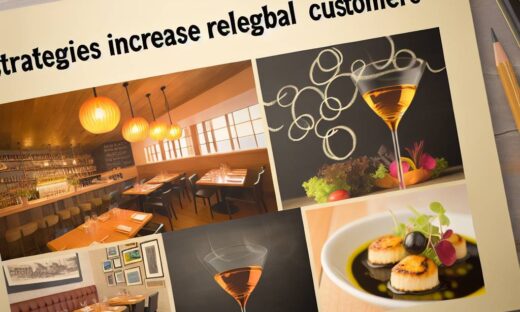
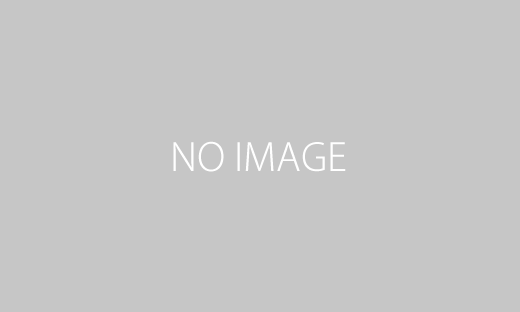






この記事へのコメントはありません。